― 物理の基礎から音響エンジニアの現場までをつなぐガイド ―
DAW の画面でウネウネ躍る波形、海岸で押し寄せる白波、スピーカーから内臓を揺さぶる低音――パッと見はバラバラなのに、どいつもこいつも「波」と呼ぶ。同じ言葉で括ってるけど、ホントに仲間? …とツッコまれた瞬間、意外と説明に詰まってしまうのが人間。
高校物理を「テスト終わったら全部忘れたよ!」でスルーした人も、収録やライブを毎日回してるエンジニアも、“波って何者?” と問われると、あれ?ってなる。
そこで本ガイドは、まず 「波とは何か。」 へ原点回帰。 カギになるのは 横波・縦波・疎密波 の三兄弟。水面の波紋から、拍手が客席を走り抜ける理由、そして DAW の波形の謎まで、日常ネタでスッキリひもときます。
目指すのは 「数式アレルギーでも、読後すぐ現場でドヤれる」 記事。 さっそく 「波ってそもそも何?」 の核心へ潜っていきましょう。
波ってそもそも何?
定義: 波とは、媒質内のある点から別の点へとエネルギーを段階的に伝達する擾乱または変動のことであり、弾性的な変形や、圧力・電場または磁場の強度・電位・温度の変化などの形をとることがある。引用元:ウェブスター辞典
これだけ読んだだけだと、“波って何?”状態。そこで、実生活エピソードを元に、『あ、波ってこういうことか!』とストンと落ちる解説をお届けします。
波の性質
まずはイメージから。図Aの波形は、波の山と谷が左側を開始地点として、右側に向かっていくというイメージの波形です。
この波形の横軸のどこか1点を観測すると、時間とともに「山、谷、山、谷…」とリズムを刻む様子が観測できます。
この「山と谷の模様が次々に伝わる」現象こそが 波 。たとえば、水面に石をポチャンと放り込めば、中心から同心円状に広がる波紋が観測できます。
周囲に波を伝搬させる物質のことを “ 媒質 ” と呼び、この場合は水のことを表します。
図Aの最大振幅*¹の点を山、最低振幅の点を谷と呼び、山と山の間隔を“ 波長 (\( \lambda \) [m])” 、山から山までの時間を“ 周期 (\(T\) [s])”、媒質が1秒間に振動する回数を“ 周波数 ”(\(f\) [Hz]) ”、波の伝わる速さを “\(V\) [m/s]” とすると、以下の関係があるといえます。
*1振幅: 物体が振動しているときの、振動の中心から最大変位までの距離。振動の幅の半分。振り幅。引用元:デジタル大辞泉
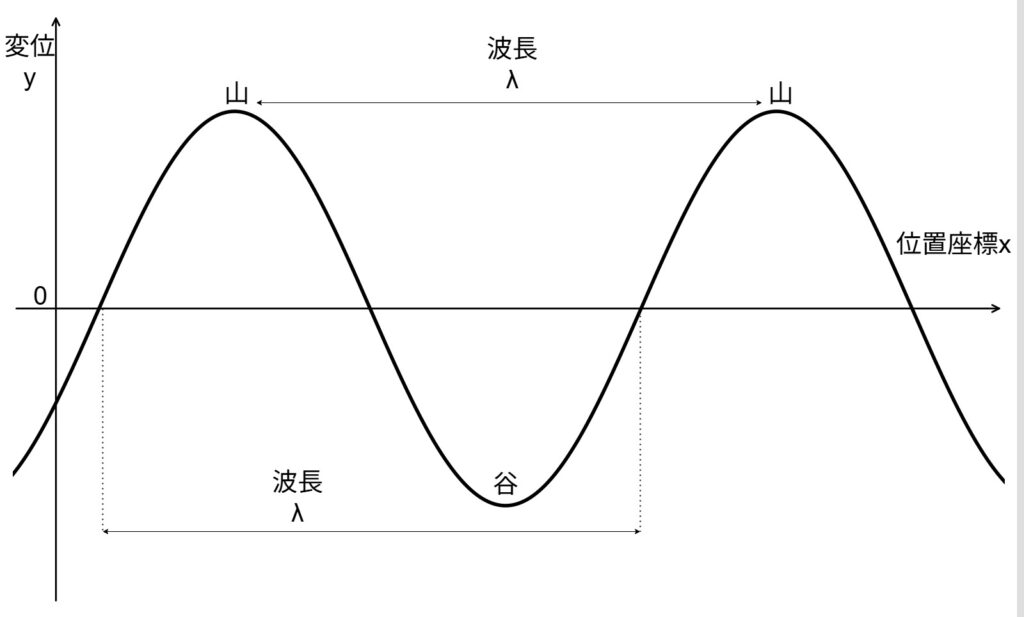
Ⅰ.周期(\(T\)[s])は周波数(\(f\) [Hz])に反比例する
$$ T = \frac{1}{f} $$
例:50 Hz のハムノイズは \(T=1/50=0.02\) s (20 ms)。
Ⅱ.波の速さ( \(V\)[m/s])は、波長(\(\lambda\)[m])を周期(\(T\)[s])で割ったもの
$$ V = \frac{\lambda}{T} = \lambda f $$
つまり、波長 \( \lambda \) を周期 \( T \) で割れば進む速さV、周波数\(f\)を掛けても同じ結果が得られます。
Ⅲ.周波数から波長を逆算
$$ \lambda = \frac{v}{f} $$
例:20 kHz の高音なら \(\lambda \approx 343/20000 \approx 0.017\) m (1.7 cm)
波を構成する用語をまとめると
| 振幅 \(A\) | 振動中心から山までの距離。単位は m(変位)や Pa(音圧)など。 |
| 波長 \(\lambda\)[m] | 隣り合う山 ⇔ 山 の水平距離。単位は m。 |
| 周期 \(T\) [s] | 1回の山→谷→山のサイクルに要する時間。単位は s。 |
| 周波数\(f\) [Hz] | 1秒間に繰り返す山の数。単位は Hz。(\(f=1/T\)) |
| 波の速さ\(V\)[m/s] | 波が進む速さ。単位は m/s。(前述の式で求まります) |
定義のおさらいと実際の現象
ここでもう一度定義をおさらいします。
波とは、媒質内のある点から別の点へとエネルギーを段階的に伝達する擾乱または変動のことであり、弾性的な変形や、圧力・電場または磁場の強度・電位・温度の変化などの形をとることがある 。引用元:ウェブスター辞典
この定義の最も重要な点は、波とは「媒質中を伝わっていくゆれや変化である」ということです。波が通過する時、媒質は局所的に振動することはあっても、粒子そのものが波と一緒に移動するわけではありません。
身近な例で実感しよう
■ 水面の波紋
先ほど話した波紋について分解すると、こういった現象といえます。
- 石がポチャンと落ちた瞬間、水面がピョコンと盛り上がり、すぐにシュルッと沈む。
- その動きが周囲の水にも伝わり、周りの水が同じように揺れ始める。
- こうして同心円状の波紋が広がる— 見た目は水が動いているようですが、実際には「揺れのパターン」が伝播しているだけ。
水の粒子(分子)そのものが外側へ運ばれていっているわけではありません。動いているように見えるのは「揺れの動き」であって、「水」自体ではないという点が重要です。
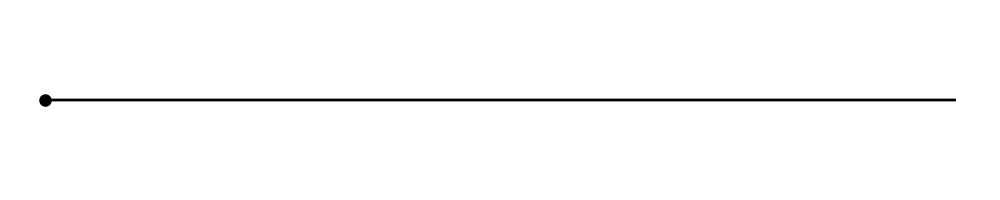
■ 空気中の音波
- スピーカーから出た音が空気中を進むとき、空気分子は元の位置を中心に前後に小刻みに揺れます。
- その揺れが次の分子に伝わり…とリレーされ、最終的に耳に到達。
- ここでも実際に前後移動しているのは「揺れ」であって、空気がガーッと吹き飛ぶわけではありません。
※だから「音圧レベル」を測るわけで、「風速」を測ってるわけではないんです。
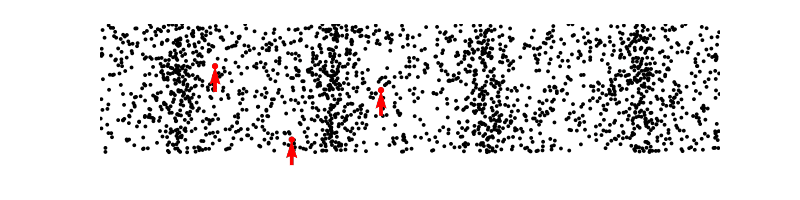
今説明した二つの波、実は分類が違います。
ざっくりまとめると、
水面の波紋: 横波 (Transverse wave)
空気中の音波: 縦波 (Longitudinal wave)
この2つ、媒質の「揺れる向き」が違うだけで、波の本質は同じ「揺れの伝播」です。
次はここから、縦波と横波の特徴を見ていきましょう!
横波と縦波、それぞれの特徴。
横波 (Transverse Wave)
- 媒質の振動方向と波の進行方向が垂直な波
- 媒質の各点が上下(または左右)に振動する
- 波は垂直方向の「山と谷」を次々に前方へ運ぶ
- 主な例
- 弦の振動(ギターの弦など)
- 水面波(プールや海のさざ波)
- 電磁波(電波や光など、媒質を要しない横波)
縦波( Longitudinal Wave)「疎密波 Compressional / Pressure Wave」
- 媒質の振動方向と波の進行方向が平行な波
- 媒質の各点が前後に押し引きされる
- 空気の密度が濃淡になる「疎→密→疎」が連続
- 主な例
- ばね模型
- 空気中の音波(音源→耳)
- 地震のP波
- 疎密波(圧力波)という呼称
- 縦波のうち、媒質の「圧力変化」に注目して説明する場合に用いる
- 音響工学などで一般的に用いられる。
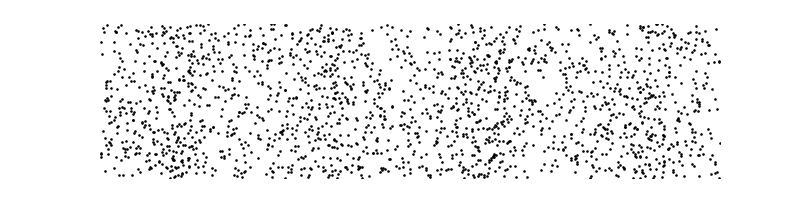
下図は、横波と縦波(疎密波)を振動方向と進行方向の関係で比較したイメージです。
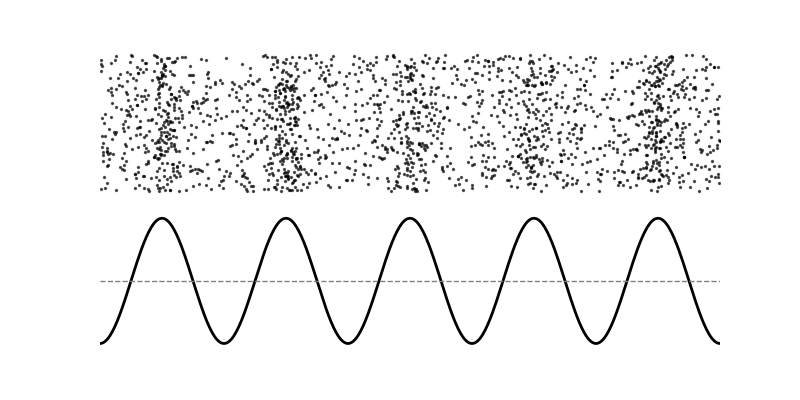
(図:横波は波の進行方向に対し媒質が上下に振動し、縦波は進行方向と同じ向きに圧縮・膨張が伝わる)
空気で「波」をイメージしてみる
| キーワード | 要点 | 身近なイメージ |
|---|---|---|
| 媒質 | 波を伝える“道”となるもの――ここでは 空気分子 | 風船を膨らませたときの空気や場に満ちる大気 |
| 振動 | 分子が「ギュッ(密)⇄シュル(疎)」と前後に小刻みに揺れる。まるでドミノ倒し | スピーカーのコーンが前に押し出され、戻ってくるあのブワッとした感じ |
| エネルギーのリレー | 揺れた分子が隣の分子にバトンタッチ…リレーのように伝播する様子が波の本体 | 拍手を一度叩くと、その音が遠くまで届く現象 |
※ 補足:実際の空気分子は通常、数十ナノメートルから数十マイクロメートル程度しか動きません。
なぜ「音波=縦波」を“横波グラフ”で見るのか?
- 縦軸は“向き”ではなく“量”を描くキャンバス
音波は空気の圧縮⇄膨張(前後揺れ)が起こりますが、オシロスコープやDAWでは「時間または距離に対する 圧力偏差 [Pa] 」を上下で表します。すると自然に正弦波状に見え、まるで横波のように描けちゃうんです。
POINT
波の「向き」 と、グラフの 「上下」を混同しないこと。
グラフはあくまで “量の変化” を記録した図表です。
まとめ ― 高校物理から現場へ一直線
- 縦波・横波は「粒子の揺れる方向」でバッチリ区別!
- 横波:媒質の振動方向と波の進行方向が垂直な波
- 縦波/疎密波:媒質の振動方向と波の進行方向が平行な波
:媒質が進行方向と同じ向きに圧縮⇄膨張
- 音波は縦波だけど、DAWの波形は“圧力の山谷(上下偏差)”を横波っぽく表示しているだけ。見かけ倒しに注意!
- 波を構成する用語[\(A\),\(\lambda\),\(T\),\(f\),V]をおさえておけば、プラグインやホワイトペーパーにしれっと記されている物理量が何を表しているのかわかります。

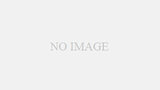
コメント